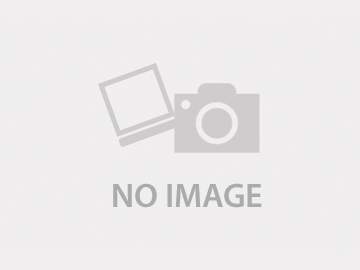障害者雇用には合理的配慮が求められます。
合理的配慮とは、障害を持つ人が働きやすくなるために必要なものです。
障がいを持つ人が働きやすいように配慮があるのですが、合理的配慮はわがままなんじゃないか・・・と悩む方もいるようです。
この記事では
- 合理的配慮とは
- 合理的配慮を進めるためのステップ
- 合理的配慮を求める際の準備することは?
- 働くための配慮とわがままの違いの事例
について解説していきます。

合理的配慮とは
障害者雇用では、障がいを持っていて困っていることの配慮を「合理的配慮」として企業に求めることができます。
合理的配慮とは、例えば、車椅子の方が通れるように職場の通路を広くしたり、障がい者用トイレを設置したり、精神疾患で満員電車が怖い人はフレックスタイムや時差出勤を認めたり、8時間働くことが難しい人は時短勤務で対応してもらうなどのことをいいます。
障害者雇用の合理的配慮で障がいを持つ方が働きやすい状況を作らなければならないのは、「障害者差別解消法」や「障害者雇用促進法」で保障されているのです。
2021年5月に、合理的配慮の提供を民間事業主に義務付ける改正障害者差別解消法が、参議院本会議で可決・成立しています。
合理的配慮を進めるための段階
障がいを持つ人が働く上で、企業側に合理的配慮を求める場合、どのように進めていけばいいのでしょうか。
1:採用時に申し出ておく
しっかり必要な合理的配慮を申し出ておくことと、自分の障害について詳しく伝えることが必要です。
面接の段階でどんな合理的配慮が必要か聞かれることが多いので、その時に伝えるといいでしょう。
聞かれた時に、受かりたいからといって軽くいうのはやめましょう。なぜなら、しっかり長く働きたいなら、正しい配慮をしてもらわないと難しいからです。
また、履歴書の本人希望記入欄にあらかじめ記入しておくこともいいでしょう。
申し出が原因で不採用になることはないので、採用された時に長く務めることができるよう、しっかり希望は伝えましょう。
2:企業側と話し合う
希望する合理的配慮について、企業側と話し合います。
求めた配慮が企業側で対応できないこともあります。
その場合、可能は範囲での配慮案が企業側から提示されることがあります。
その場合は企業側と話し合って、どこまで配慮して、配慮できない部分はどうするのかの折衷案を出す必要があります。
情報共有やフォロー体制を整えてもらう
合理的配慮で企業との話し合いで決定した内容については、会社の同僚や上司に情報を共有してもらう必要があります。
配属される部署にどこまで伝えて欲しいのかの意思表示を行い、働く上での合理的配慮を理解してもらうことが大切です。
職場の同僚や上司が知らなければ、職場での合理的配慮などは難しいでしょう。
直属の上司など、サポートの担当者を決めてもらうと、フォロー体制も構築しやすいですし、困ったことがあった時相談がしやすいです。
4:定期的に見直しの機会を作ってもらう。
入社前に合理的配慮を決めてもらっても、実際働いてみると思っていなかった困難が待っていることがあります。
そのため、入社してからも定期的に話し合いの場を作ってもらい、新たに出てきた問題について話ができるような体系を作っておいてもらいましょう。
合理的配慮は職場の定着率にもつながりますので、しっかり話をしましょう。
合理的配慮を求める際の準備することは?
合理的配慮は障害者自身から申し出る必要があります。
採用担当者や会社側はどんな配慮が必要なのかわからないため、しっかり伝えばければなりません。
特に精神障害や内部疾患については、周囲からは見えにくいので、しっかりと伝える必要になります。
配慮を求める際の事前準備として、仕事上の困難さや自分ではどうやって対処しているか、また、求めたい配慮項目について書き出してまとめてみましょう。
そして、仕事上で困難と感じることは何か、それについて自己対処できる方法はないかをまずは考えてみます。
その上で、自分で対処できないことは、「いつ・誰が・どのようにすればいいのか」を具体的に書き出しましょう。
配慮内容を話し合う上で、主治医からの診断書や意見書が必要になることがあります。
必要な際は主治医と相談して、合理的配慮の根拠を主治医に診断書や意見書を書いてもらいましょう
。

働くための配慮とわがままの違いの事例
合理的配慮を考える上で、「これは私のわがままになるのでは・・・?」と悩むこともあると思います。
合理的配慮は企業で働くための配慮なので、しっかりと働いて会社に貢献できるようにするためだと思いましょう。
それでは、合理的配慮とわがままの違いについて解説していきます。
合理的配慮
通勤ラッシュが精神的に怖いので、フレックスタイムで働きたい
→これは、合理的配慮と言えます。長く務めるために、慣れるまでは時短勤務という方も多いです。
わがまま
ストレスや疲れたら働けないので、帰りたい。
→ストレスを感じたらいつでも帰りたいだと同僚も困ってしまいます。
始めからストレス心配なら時短勤務を願い出ましょう。
合理的配慮
自分で困難なことが出たときに言い出すのが難しいので、定期的な話し合いの場を設けてもらい、そのときに改善点の話し合いをさせて欲しい。
→不安に対する対処方法として定期的に面談や相談の場を設けてもらうことは大切です。実際働いてみてわかることもあるので、定期的に話し合いの場を設けてもらいましょう。
わがまま
自分から言い出すのは難しいので、察して欲しい。よくみていて欲しい。
→これは、「自分は何も訴えないから、担当者がしっかりみておいてよ」という勝手な申し出になります。きちんと自分から発信しましょう。
合理的配慮
日によっては人との会話が難しいことがあるので、机に✖️と書いてある札を置いているときは、あまり話しかけないで欲しい。
→これは、自分できちんと対策を考えて、みんながわかりやすい提案なので、合理的配慮に当たります。
わがまま
自分から声をかけるのが苦手なので周囲から声をかけてほしいが、日によっては難しいので、その際は朝の自分の表情や態度をみて感じて欲しい
→これは、わがままな方はわかりますよね。「周りの人は自分のことをしっかりみておいてよ」というのは自己中心的でわがままです。
自分でなんらかの形で発信して職場の人にわかりやすくすることが必要です。
まとめ
この記事では
- 合理的配慮とは
- 合理的配慮を進めるためのステップ
- 合理的配慮を求める際の準備することは?
- 働くための配慮とわがままの違いの事例
について解説していきました。
障がいを抱えながら働くのは大変なことです。
そのために合理的配慮があるのですが、職場の人に負担がかからないように配慮を考えて伝えることが必要でしょう。
何も言わないから考えて配慮してねというのは避けたほうがいいでしょう。
しっかり長く働くことができるよう、合理的配慮をしっかり考え、企業側と話し合いましょう。